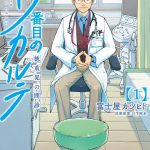【総合診療が評価される時代】
2025-07-30
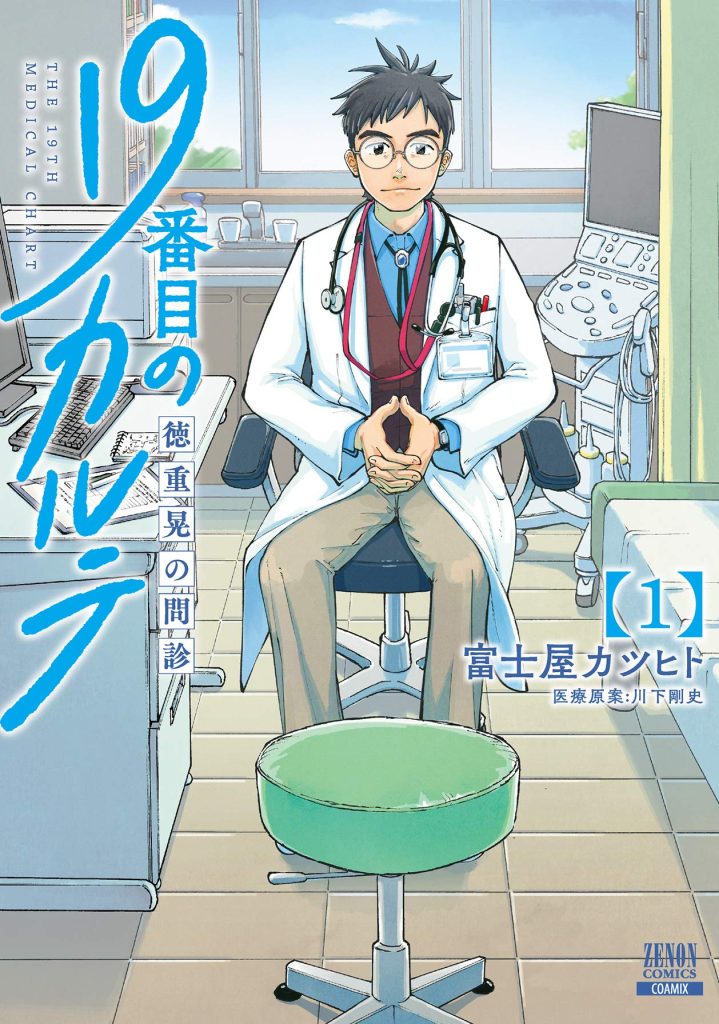
TBSの日曜劇場は、社会的に影響のあるテーマを扱った作品が多く、過去には半沢直樹、ドラゴン桜、下町ロケット、ノーサイドゲームなど、観るたびに胸が熱くなる大好きな番組の一つです。
そのTBSの日曜劇場で、7月から「19番目のカルテ」という新しい番組が始まりました。
このドラマは総合診療科というまだあまり一般的には知られていない医療分野を舞台に、患者の症状だけでなく、その背景にある心や生活・家庭環境など、その患者の背景や生き方そのものに寄り添う医師・徳重晃(松本潤)の姿を描いています。
現在の医療は専門性が益々進んできていて、専門の臓器や分野しか分からない医師が多くなってきている中で、医師の専門領域の観点では病気の原因や診断ができず、いわゆるお手上げ状態になってしまった患者に対して、主人公の徳重医師が、患者の病気の根本原因を推論するべく、家庭環境や生活習慣、患者の心の奥にある悩みやストレスといったものを患者との会話を通じて見抜き、その患者にとって最適な治療法を導き出すといった手法を展開し治療を成功させるドラマです。
今までの医学教育は、患者の病気の診断とその治療に特化していて、その病気が発生した原因となり得る食事や生活習慣、ストレスといった領域にまで過去に遡って推論していくというところまでは踏み込んでいませんので、このようなドラマは、今後の医師教育にも一石を投じるものだと思います。
実際に患者と向き合っている医師の中には、今までの西洋医学で学んだ知識だけでは限界があることを痛感している医師も多く、東洋医学や機能性医学、ホリスティック医学、代替医療などを勉強してこれらを組み合わせた治療をしている医師も少しずつ増えてきているように思います。
このドラマのように問診やそれ以外の機会を使った患者との会話の中から、患者の病気の根本原因を推論し、最適な治療法を見出すという総合診療は、とても時間のかかる作業でもあり、病院経営が厳しくなってきている現状において、それだけの時間を使って患者一人一人に診療することがはたして現実的なのかという問題も浮き彫りになってきます。
このドラマの主人公である徳重晃のモデルとも言われている生坂政臣(いくさか まさおみ)先生は、千葉大学医学部の統合診療部の特任教授で、総合診療専門医検討委員会の委員長でもある方で、このドラマの監修を務めているようです。
私は長い間、医薬品業界で仕事をしてきた関係で、薬の限界を痛感してきましたし、医療の限界も近くで知る立場でもあったため、より本質的な医療を目指すこのドラマによって、視聴者の多くの方々が「医療とはどうあるべきか」について考える良い機会になればと思っています。